食中毒は、細菌やウイルスなどの病原体が体内に侵入し、腹痛・嘔吐・下痢などの症状を引き起こす感染症です。主な原因には 細菌性食中毒 と ウイルス性食中毒 があります。ここでは、代表的な原因微生物の特徴、原因食材、治療・消毒のポイントを整理します。
原因菌・ウイルス各論
◆1. 腸管出血性大腸菌(O157、O111など)
特徴
腸管出血性大腸菌(EHEC)はベロ毒素を産生し、重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。感染力が非常に強く、少量(10〜100個程度)で感染します。ベロ毒素は腸管の粘膜を傷つけ出欠を助長します。
潜伏期間
1〜8日(平均3〜4日)
主な症状
激しい腹痛、水様便、血便
原因食品
生肉(特に牛肉の生食)、加熱不十分な食肉、野菜、井戸水など
治療
対症療法(脱水補正)。重症例では抗菌薬投与を検討するが、ベロ毒素型では溶血性尿毒症症候群リスクがあるため慎重に。
消毒
消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム(0.02〜0.1%)で有効。熱にも弱く、75℃1分以上で死滅するので、加熱料理は非常に有効です。
◆2. ノロウイルス
特徴
冬季に多発する代表的なウイルス性食中毒。人から人への感染力が非常に強く、環境中でも長期間生存するため吐物処理を次亜塩素酸ナトリウムで確実に行わないと感染する。牡蠣の生食での感染が有名。吐物に触れることで感染することも有名。
潜伏期間
12〜48時間
主な症状
嘔吐、下痢、腹痛、発熱
原因食品
二枚貝(カキなど)、感染者の手指や調理器具を介した汚染食品
治療
特異的な抗ウイルス薬はなく、脱水防止などの対症療法。
消毒
次亜塩素酸ナトリウム(0.1〜0.5%)または85℃以上で1分以上の加熱で不活化。アルコール消毒は効果が低い。(ほぼ無いと考えてよい)
◆3. ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)
特徴
芽胞を形成するため、加熱後も生き残ることがあります。大量調理(カレー、煮物など)で発生しやすい。
潜伏期間
6〜18時間
主な症状:
腹痛、水様便(通常、軽症で自然軽快)
原因食品
加熱後に室温で放置された料理(煮物、カレー、スープなど)
治療
対症療法で軽快。抗菌薬は不要。
消毒
芽胞は熱・アルコールに強く、120℃4分以上の加熱(オートクレーブ)で死滅。
◆4. 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
特徴
エンテロトキシン(耐熱性毒素)を産生。調理者の手指や鼻腔に常在する菌が食品を汚染します。2000年には加工乳が原因となる患者数13,000人の食中毒事件があった。
潜伏期間
1〜6時間(非常に短い)
主な症状
嘔吐、腹痛、下痢
原因食品
おにぎり、弁当、総菜、クリーム類など
治療
対症療法。毒素に対する治療薬はなし。
消毒
菌自体はアルコール・次亜塩素酸で除去可能だが、毒素は熱に強く100℃20分でも失活しにくい。
◆5. ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)
特徴
最も強力な神経毒を産生。嫌気性で芽胞形成菌。家庭での瓶詰・真空包装食品で発生することがあります。1984年に発生した熊本県、真空パックされた辛子蓮根が原因のボツリヌス菌食中毒事件がおこった。
潜伏期間
12〜36時間
主な症状
神経麻痺、複視、呼吸困難(消化器症状は軽度)
原因食品:
自家製保存食品、缶詰、真空パック食品など
治療
抗毒素血清投与、呼吸管理。
消毒:
芽胞は熱・アルコールに極めて強い。120℃4分以上で死滅。
◆6. サルモネラ菌(Salmonella)
特徴
代表的な細菌性食中毒。鶏卵や鶏肉が主な感染源。
潜伏期間
6〜72時間
主な症状
発熱、腹痛、下痢、嘔吐
原因食品
生卵、加熱不十分な肉、乳製品
治療
対症療法。重症例ではニューキノロン系や第三世代セフェムを使用する場合も。
消毒
次亜塩素酸ナトリウム有効。75℃1分以上の加熱で死滅。
◆7. カンピロバクター(Campylobacter jejuni/coli)
特徴
国内で最も多い細菌性食中毒の一つ。少量で感染。まれにギラン・バレー症候群を起こすことがあります。
潜伏期間
2〜7日
主な症状
発熱、倦怠感、腹痛、水様便、血便
原因食品
加熱不十分な鶏肉、生レバー、井戸水など
治療
対症療法。重症例ではマクロライド系(エリスロマイシンなど)が有効。フルオロキノロン耐性株の増加が懸念される。
消毒
熱・次亜塩素酸に弱い。75℃1分以上で死滅。
◆まとめ:予防の基本
- 食材は中心部までしっかり加熱(75℃1分以上)
- 調理器具・手指は次亜塩素酸ナトリウムで消毒
- 調理後はすぐに食べる、または速やかに冷却保存
- 二次汚染を防ぐ(生肉・野菜・調理済み食品を分けて扱う)
- ノロウイルスには消毒用アルコールが効かないことは覚えておこう


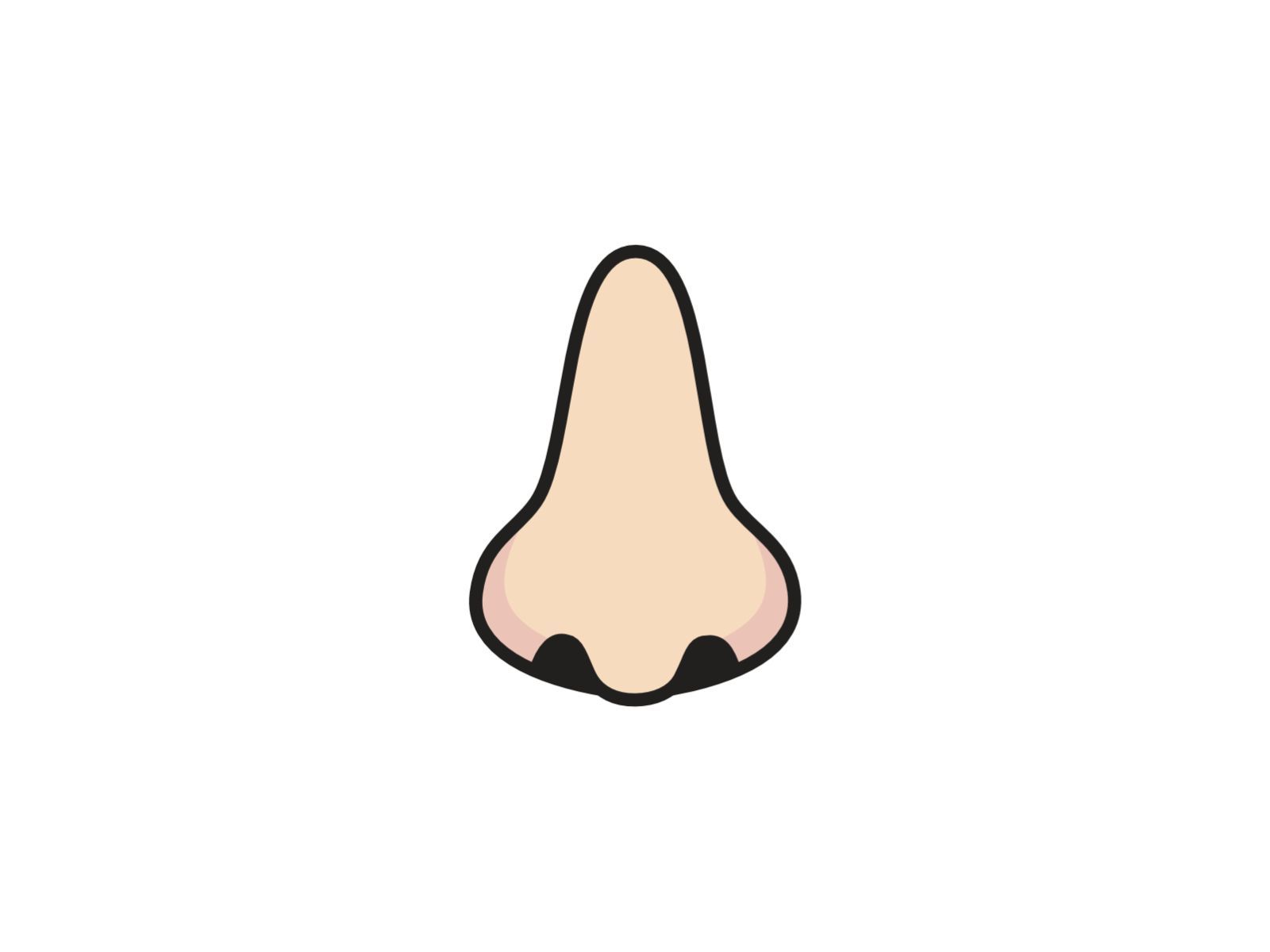
コメント