こんにちは。学校薬剤師のIWAKIです。
近年、「子どもたちのOD(オーバードーズ)」というニュースを耳にする機会が増えました。
一昔前までは考えられなかったことですが、今では小学生や高校生が身近な薬を過剰に服用し、命に関わる事例まで起きています。
この記事では、ODとは何か、なぜ起きているのか、そして家庭でできる対策について、薬剤師の立場から解説します。
OD(オーバードーズ)とは?
OD(Overdose)とは、「過剰摂取」のことです。
病院で処方される薬、薬局やドラッグストアで買える市販薬、サプリメントなどを大量または頻回に服用することを指します。
最初は少量でも、服用を繰り返すうちに次第に効かなくなり、量が増えていく。
その結果、心身への影響が大きくなり、命の危険に至るケースもあります。
薬物乱用とは?
「薬物乱用」とは、決められたルールを守らずに薬を使用することです。
覚醒剤や大麻などの違法薬物だけでなく、本来の治療目的以外で医薬品を使う行為も薬物乱用にあたります。
つまり、ODも薬物乱用の一種です。
薬物には「依存性」と「耐性」という性質があります。
- 依存性:一度使うと、自分の意思でやめにくくなる
- 耐性:使い続けると、同じ量では効かなくなる
「1回だけなら大丈夫」と思っても、次第に使用量・回数が増え、抜け出せない悪循環に陥ってしまうのです。
その結果、脳の細胞が破壊され、学習能力の低下、成長への悪影響、精神の変調といった深刻な問題を引き起こします。
乱用されている薬はどんなもの?
意外かもしれませんが、乱用されているのは咳止め薬や風邪薬などの一般的な市販薬です。
これらには、麻薬や覚醒剤と似た作用を持つ成分がごく微量に含まれています。
そのため、何十錠も一度に服用すると、一時的に気分が高揚したり落ち着いたりすることがあります。
しかし、それは一時的なもの。
繰り返すうちに「もっと飲まなければ落ち着かない」という依存のサイクルに陥っていくのです。
なぜ量が増えていくのか?
乱用を続けていくと、**同じ量では効かなくなる「耐性」**がついてしまいます。
その結果、次第に服用量が増えていきます。
さらに中断すると、気分が落ち込んだり、体調が悪くなったりする離脱症状が出ることもあります。
つまり、市販薬であっても依存性があり、やめにくくなるのです。
体への影響
薬は通常、「肝臓」で代謝され、「腎臓」から尿として排泄されます。
正しい量であれば問題ありませんが、ODによって過剰に薬が入ると、
- 肝臓への負担(肝障害)
- 腎臓への負担(腎障害)
- 心臓や脳への影響
といった深刻なダメージを引き起こします。
体が薬を処理しきれず、毒性が全身に回ることで、命に関わる状態になることもあります。
SNS時代の落とし穴
SNSが普及した今、「つらい」「死にたい」「家出したい」などの投稿に対して、
「相談乗るよ」「楽になる薬があるよ」「痩せる薬あるよ」といった危険なダイレクトメッセージが送られてくるケースがあります。
本人も「これは危ない」と分かっていても、精神的に追い詰められているときはつい反応してしまうことがあります。
こうした状況の中で、何が正しい情報で、何が誤った情報なのかを見極めることが非常に大切です。
SNS上の「薬情報」は、信用できる医療専門家のもの以外、鵜呑みにしないよう注意しましょう。家族や友達に相談してみるののいいでしょう。一人で悩まないでください。
衝撃的なニュース
- 令和5年12月16日(朝の情報番組)
小学生によるODが報じられ、薬剤師としても衝撃的なニュースでした。 - 令和5年12月8日(朝刊)
高校生が咳止め薬を大量に服用し、命を落とすという痛ましい事件が報道されました。 - 令和5年2月11日(朝刊) 2024年に都内で補導された少年少女は延べ40人(昨年度の約2倍)
これらの事件は、「身近な薬でも使い方を誤れば命を奪う」という現実を突きつけています。
家庭でできること
数年前までは想像もしなかったことが、今は現実に起きています。
家にある咳止め薬・風邪薬・鎮痛薬も、使い方を誤ればODの引き金になります。
家庭内で「薬」について話す時間をぜひ持ってください。
- 頭痛薬や生理痛薬を過量に飲むと、薬剤誘発性頭痛を引き起こすことがあります。
- サプリメントも摂りすぎれば体調不良の原因になります。
サプリメントは食事より吸収が速く、過剰に摂ると、顎の筋肉の衰え・消化管の萎縮・消化液分泌の低下などが起こる可能性もあります。
最後に:薬は「正しく使えば味方、間違えば毒」
薬は正しく使えば体を守りますが、使い方を誤ると毒になります。
「用法・用量を守る」「薬を貸し借りしない」――この2つは何より大切なルールです。
子どもたちを守るために、家庭や学校で「薬との付き合い方」について、今一度考えてみましょう。

学校薬剤師は「薬物乱用防止教室」や「防煙教室」などの活動を各小学校や中学校、高校で行っています。各学校には必ず「学校薬剤師」が配置されているので先生や保護者の方も是非相談してください。学校では「養護教諭」の先生が窓口になることが多いです。
参考文献
- NHK健康チャンネルWeb
- 東京都保健医療局ホームページ
- 日本経済新聞
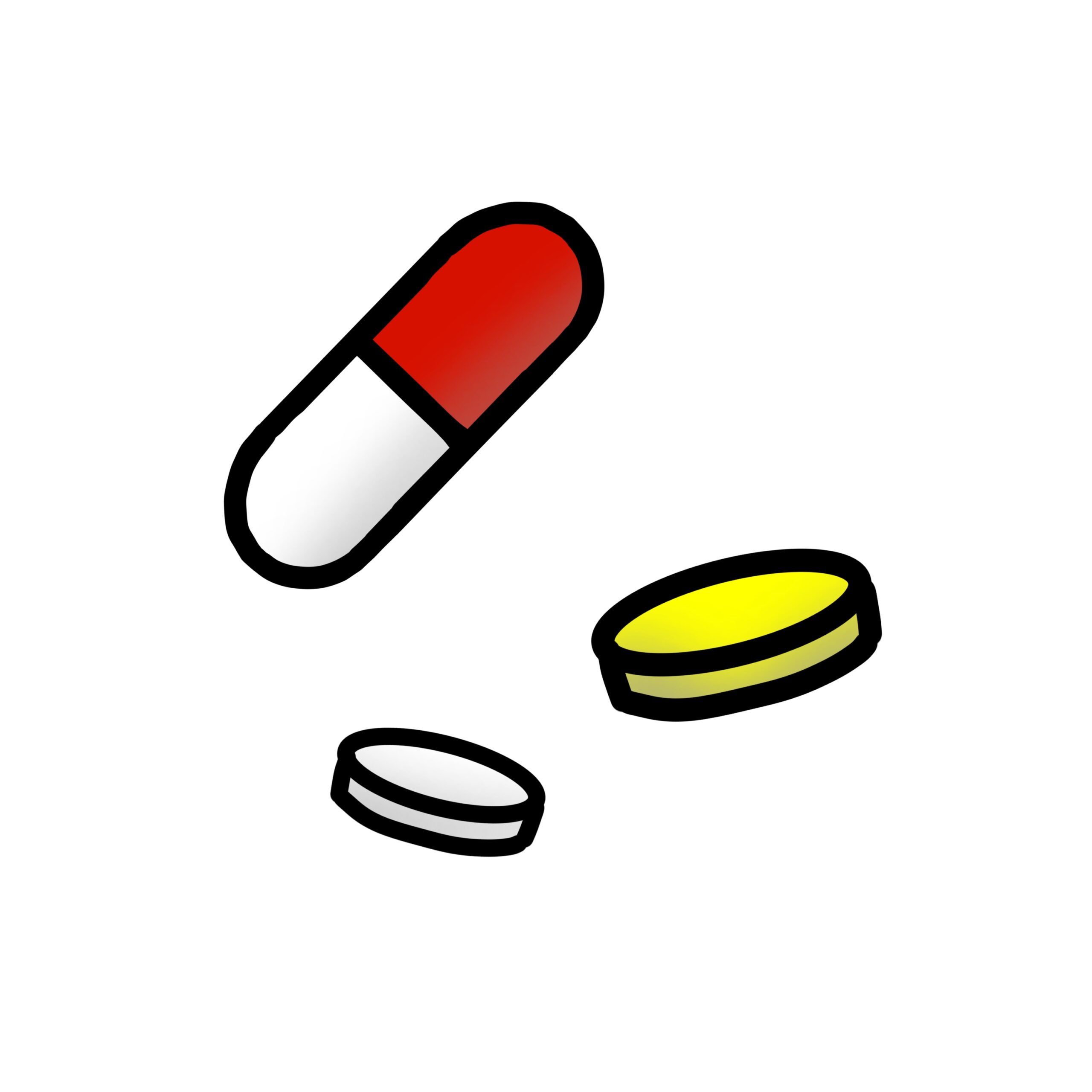


コメント