はじめに
病院における感染委員会(ICC)・感染対策チーム(ICT)は、院内感染防止の要です。近年、医療安全や感染対策への社会的な関心が高まり、保健所による立ち入り調査もより詳細かつ厳格になっています。
調査時には、単にマニュアルや会議記録を確認されるだけでなく、実際に機能しているかどうかが問われるため、事前の準備が重要です。
本記事では、保健所立ち入り時に感染制御部が特に注意すべきチェックポイントを整理します。
1. 事前調査の内容について詳しく質問される
保健所の調査は、事前に提出した書類やデータをもとに進められます。提出資料と現場の実態が乖離していると、詳細な質問や追加調査につながります。
- 提出前に 内容の正確性を再確認
- 記載内容をスタッフ間で共有し、誰に質問されても回答できるように準備
- 実際の運用と矛盾がないかチェック
2. ICC・ICT月例会議の出欠状況
感染制御の組織運営で重視されるのが、感染対策委員会(ICC) および ICT月例会議です。
- 出席率に大きな偏りがないか(欠席が多いスタッフがいないか)
- 特定の職種や部署が参加していない状況が続いていないか
- 議事録がしっかりとられているか
- 会議の欠席者へのフォローアップは行われているか
偏りがあると「組織横断的な活動ができていない」と指摘される可能性があります。
3. 院内感染対策マニュアル(指針)の更新頻度とスタッフの閲覧方法
院内感染対策マニュアル(指針)は「作成して終わり」ではなく、定期的な見直しが必須です。
- 最低でも年1回は更新履歴を残す
- 法改正やガイドライン改訂時は速やかに反映
- スタッフが いつでも閲覧可能(院内ポータル、電子マニュアル)になっているか確認
更新はされていても「現場が知らない」状態では不十分と判断されます。

当院では紙媒体での部署配置でしたが、電子化を行ったことにより各部署で最新のマニュアルが閲覧できるようになりました。
4. 緊急事態発生時の対応と連絡網
院内で集団感染やアウトブレイクが起こった際の初動対応は、調査で必ず確認されます。
- 緊急時マニュアルの整備
- 発生時の 連絡網(職種別・時間外対応を含む) の明確化
- 机上演習やシミュレーション訓練の実施履歴
実効性があるかどうかを問われるため、「訓練を行ったか」「その記録があるか」がポイントになります。

マニュアルには緊急時の連絡網を掲載していますが、職員のプライベート保護のため個人の電話番号は掲載していません。個人の連絡先は別刷りで各個人が携帯しています。
5. 抗菌薬適正使用(AS)の集計とフィードバック
抗菌薬適正使用(Antimicrobial Stewardship, AS)は全国的に強化されています。
- 使用量や抗菌薬別の投与状況を集計
- ICTや薬剤部が中心となり、抗菌薬使用実態を院内にフィードバック
- 不適正使用への是正指導を記録に残す
単なる「データ集計」ではなく、「改善サイクルが回っているか」が評価対象です。
6. 手指衛生の遵守率と速乾性手指消毒剤の使用量
手指衛生は最重要項目です。
- 速乾性手指消毒剤の使用量を定期的に集計
- 部署ごとに差が出ていないか確認
- 院内掲示やICTニュースでフィードバックし、可視化
調査員は「単に消毒剤を置いているか」ではなく、「使用実績を分析し改善につなげているか」を重視します。
7. 院内感染対策研修会の実施とフォローアップ
感染対策研修は 年2回以上の開催 が推奨されています。
- 出席率を記録し、欠席者には 動画配信・資料配布・小テスト などでフォロー
- 出欠簿をエビデンスとして保管
形式的な開催ではなく、全スタッフが参加できる仕組みを示すことが重要です。

研修会は勤務時間外に行われることが多いため、出欠率がなかなかあがりません。欠席者へのフォローアップをどのように行うかが問題となります。当院では欠席者への資料配布とグーグルフォームを利用した小テストを行っています。
8. 耐性菌発生時の対応とアンチバイオグラム
多剤耐性菌(MRSA、ESBL、CREなど)が検出された際の対応は厳しく確認されます。
- 発生時の隔離方法や対応手順の明確化
- 感染経路調査と対策の記録
- 年1回以上の アンチバイオグラム作成(院内の耐性菌傾向をまとめた報告書)
「データを収集し、現場に還元しているか」が問われます。

当院では、医師と薬剤師による耐性菌ラウンドを実施しており耐性菌(MRSA,2剤耐性緑膿菌など)発生時には巡回し、病棟師長やリハスタッフへの耐性菌水平伝播の抑制についてアドバイスを行っています。
9. 環境ラウンドの実施と対応
環境ラウンドは、週1回の実施が推奨されます。
- 出席者リストを残す(職種の偏りがないか)
- 指摘事項が出た場合、改善計画とフォローアップ を記録
単に巡回しただけではなく、「改善につながっている」ことが大切です。院内感染対策研修会やICTニュースを利用し院内スタッフに対し「可視化」したフィードバックを行うと効果的です。
10. ICTニュースなど院内広報活動
感染対策は「全職員参加」が原則です。そのための広報活動もチェック対象になります。
- ICTニュースやメール配信、掲示板での情報共有
- 発行頻度(月1回や隔月など)
- 内容は「感染症流行情報」「抗菌薬使用状況」「手指衛生キャンペーン結果」「環境ラウンド時に指摘事項が多い部分について」など
調査では「情報発信を継続しているか」「全職員に届いているか」が確認されます。
まとめ
保健所の立ち入り調査では、単に「やっている」ことを示すだけでなく、組織として機能しているか、改善のサイクルが回っているか が評価されます。
- 出欠率や使用量などの 数値的エビデンス
- マニュアルや会議記録などの 文書エビデンス
- フィードバックや改善活動という 実効性
これらをバランスよく整備することが、調査での信頼につながります。院内感染対策チームは、日々の活動を「見える化」し、院内全体で感染対策に取り組む体制を示すことが重要です。実際に保健所立ち入り日には以上のことを聞き取りされた後に、「現場確認」を行います。数チームに分かれて現場確認を行い、聞き取り内容に即した状況になっているかを確認されます。
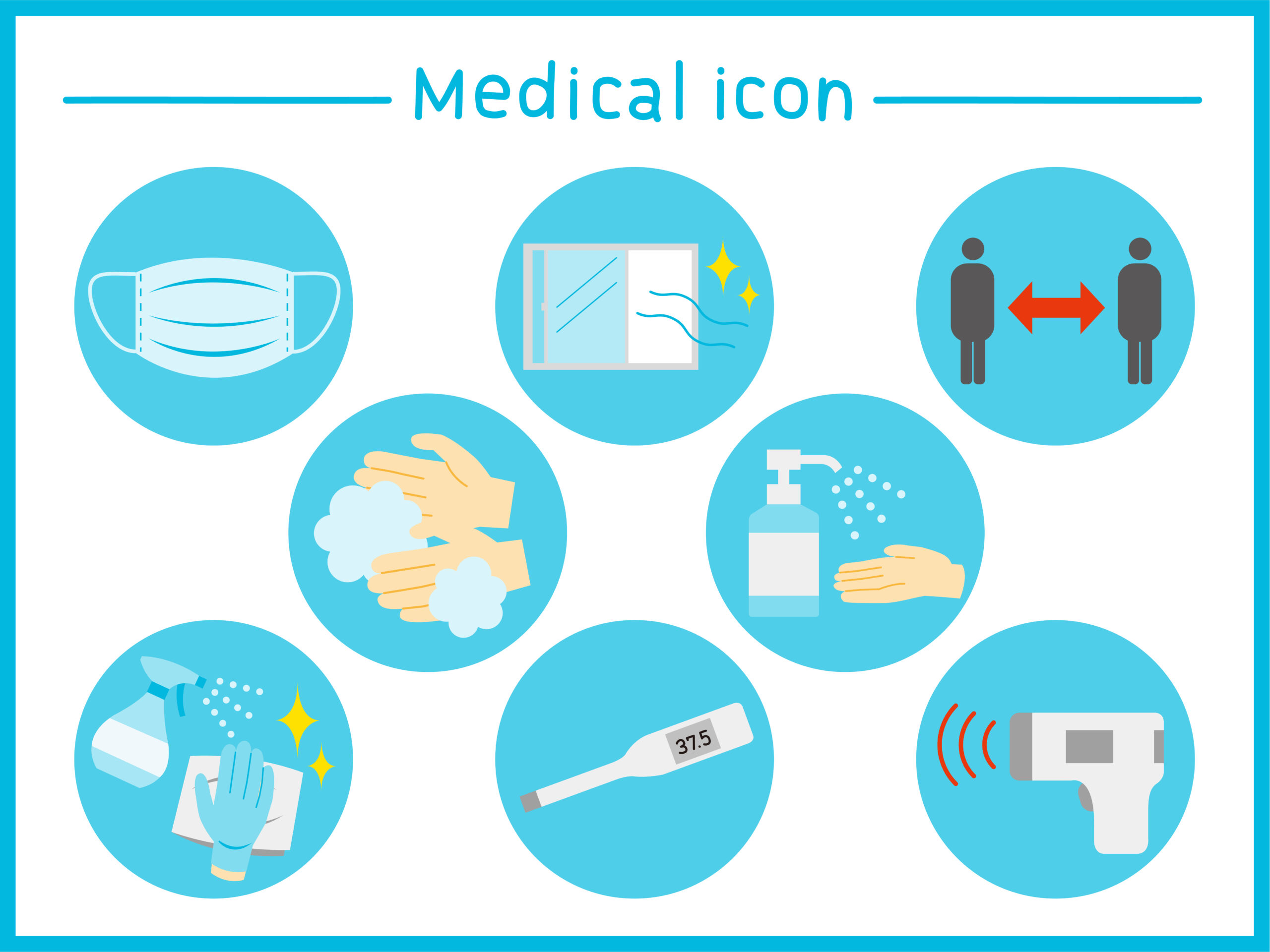


コメント