はじめに
結核(けっかく)は、かつて「不治の病」と恐れられていた感染症です。現代では治療法が確立され、多くの患者さんが治癒できる病気となりましたが、日本でも毎年1万人以上の新規患者が発生しており、決して過去の病気ではありません。本記事では、結核の原因、診断方法、治療についてわかりやすく解説します。
結核とはどんな病気か
結核は、**結核菌(Mycobacterium tuberculosis)**という細菌によって引き起こされる感染症です。主に肺に感染して「肺結核」を発症しますが、リンパ節・腎臓・骨・脳など全身に広がることもあります。
感染は空気を介して広がります。結核患者が咳やくしゃみをしたときに、結核菌を含む飛沫(飛沫核)が空気中に漂い、それを吸い込むことで感染します。ただし感染してもすぐに発症するわけではなく、多くの場合は体の免疫が菌の活動を抑え込んでいます。免疫力が低下したときに発症することが多いため、糖尿病、がん、HIV感染、ステロイド治療中の人は注意が必要です。
結核の症状
肺結核の典型的な症状は以下の通りです。
- 2週間以上続く咳や痰
- 血の混じった痰(喀血)
- 微熱、寝汗
- 体重減少、食欲不振
- 全身のだるさ
ただし、初期は風邪に似た軽い症状しか出ないことも多く、診断が遅れる原因になります。
結核の診断方法
結核の診断は、以下の検査を組み合わせて行われます。
1. 胸部X線検査
肺に特徴的な影(浸潤影、空洞など)があるかを確認します。ただし、画像だけでは結核かどうか確定できません。
2. 喀痰検査
患者の痰を採取し、結核菌が含まれているかを調べます。
- 塗抹検査:顕微鏡で菌を直接確認
- 培養検査:菌を培養して判定(時間は数週間かかる)
- 核酸増幅法(PCRなど):菌の遺伝子を検出(迅速で精度が高い)
3. IGRA(インターフェロンγ遊離試験)
IGRAは、結核菌特異的な抗原に対するT細胞の免疫反応を調べる血液検査です。結核菌に感染していると、抗原に反応したT細胞が インターフェロンγ(IFN-γ) を放出します。その量を測定することで、結核菌に感染しているかどうかを推定できます。
ツベルクリン反応(皮内注射)に代わり、より特異性が高い検査として広く使われています。
原理
- 採血した血液に、結核菌特異的抗原(ESAT-6、CFP-10 など)を加える
- 感染者のT細胞は抗原を認識し、IFN-γを産生
- その濃度を測定して陽性/陰性を判定
IGRAの特徴
長所
- 特異度が高い:BCGワクチン接種の影響を受けにくい
- 簡便:皮内注射や数日の待機が不要(採血のみ)
- 結果が早い:1日〜数日で判定可能
短所
- 活動性結核か潜在性結核かを区別できない
- 免疫抑制患者では偽陰性の可能性(HIV感染者、高齢者、免疫抑制剤使用中など)
- コストが高い(ツベルクリン反応に比べて)
主な検査法(日本で使用される2種類)
- QuantiFERON®-TB(QFT)
- 採血後、抗原刺激した全血からIFN-γ濃度を直接測定
- 結果は数値(IU/mL)で出る
- T-SPOT®.TB
- 抗原刺激した末梢血単核球から産生されるIFN-γをELISPOT法で測定
- IFN-γを産生する細胞数をカウント
両者とも精度は高く、臨床現場で広く使われています。

ツベルクリン反応、IGRA、QFTは活動性結核と潜在性結核感染症の区別ができないため、他の検査法と組み合わせて使用する必要がある。
IGRAの活用場面
医療従事者・介護従事者のスクリーニング
→ 高リスク環境での感染有無の確認
潜在性結核感染症(LTBI)の診断
→ 特にBCG接種歴のある人で有用
活動性結核が疑われる場合の補助診断
→ 胸部X線・喀痰検査と組み合わせて評価
潜在性結核感染症とは?
結核菌に感染していても発症していない状態を「潜在性結核感染症(LTBI)」と呼びます。症状はなく人に感染させることもありませんが、将来発症するリスクがあるため、場合によっては予防的に治療を行います。
結核の治療
結核は「抗結核薬」を組み合わせて、長期間内服することで治療します。治療の基本は「複数の薬を同時に、十分な期間使用する」ことです。
標準治療
下記のA法又はB法を用いる。※1重篤な肝不全、非代償性肝硬変、AST・ALTが3倍以上、慢性肝炎、80歳以上の高齢者、妊婦はピラジナミド(PZA)を避ける。
A法(初期2か月間は4種類の薬を使用し、その後は4か月2種類で維持します。)
- リファンピシン(RFP)
- イソニアジド(INH)
- ピラジナミド(PZA)
- エタンブトール(EB)(or ストレプトマイシン注 SM)
- リファンピシン(RFP)
- イソニアジド(INH)
B法(※1に該当する方。初期は2か月間は3種類の薬を使用しその後7か月2種類を継続)
- リファンピシン(RFP)
- イソニアジド(INH)
- エタンブトール(EB)(or ストレプトマイシン注 SM)
- リファンピシン(RFP)
- イソニアジド(INH)
治療開始から数週間で症状は改善しますが、途中で自己判断で中断すると菌が生き残り、再発や薬剤耐性結核の原因になります。そのため、医師の指示に従って最後まで飲み切ることが非常に大切です。
薬剤耐性結核について
抗結核薬が効かない「耐性菌」による結核は、治療が難しくなります。特に、イソニアジドとリファンピシンの両方に耐性を持つ「多剤耐性結核(MDR-TB)」は世界的に問題となっています。治療期間は長期化し、副作用も強くなるため、公衆衛生上の大きな課題です。
治療を続ける工夫
結核治療は半年以上に及ぶため、患者さんの服薬アドヒアランス(継続率)が重要です。日本では「DOTS(直接服薬確認療法)」という制度があり、医療者や保健師が服薬を見守り、確実に治療を続けられるよう支援しています。
結核伝播予防の基本
感染源対策
結核予防法から感染症法に統合され2類感染症へ
医師は結核と診断したら「結核発生届」を最寄りの保健所へ届け出ること。
喀痰抗酸菌塗抹要請患者に対しては、保健所長が応急入所を勧告する。→強制力はない
感染源となる患者には「マスク」と「咳エチケット」を。
結核予防対策
結核菌を吸入してしまった場合(結核患者と一緒にいたなど)の発病率は約5-10%とされている。
発病しなかった人を潜在性結核感染症(LTBI)といい、約90-95%は発病しないといわれているが、残り5-10%が加齢や免疫力低下などに伴って数十年後に発病する。
医療関連感染対策
咳が出る患者のスクリーニングが必要、採痰ブースを分ける、マスクの配布などあrが、一般病院では難しい一面もある。高齢者の痰培養提出時には抗酸菌培養も検討するのが望ましい。
- 環境対策:陰圧室(-2.5Pa以上)、1時間に12回の換気ができる。HEPAフィルターの設置
- BCGワクチン接種(特に乳児期)
- 結核菌の消毒にはアルコール又は両面界面活性剤(長時間)
- N95マスクの着用、サイズ違いは無意味なのでフィットテストなども利用
まとめ
結核は今も年間1万人以上が新たに診断される、決して過去の病気ではありません。咳や痰が長く続く場合は早めに受診し、正しい診断を受けることが大切です。また、治療は半年以上かかりますが、医師の指示に従いしっかり続ければ治癒できます。
感染症対策が重要視される現代において、結核に関する正しい知識を持ち、自分や周囲の健康を守っていきましょう。


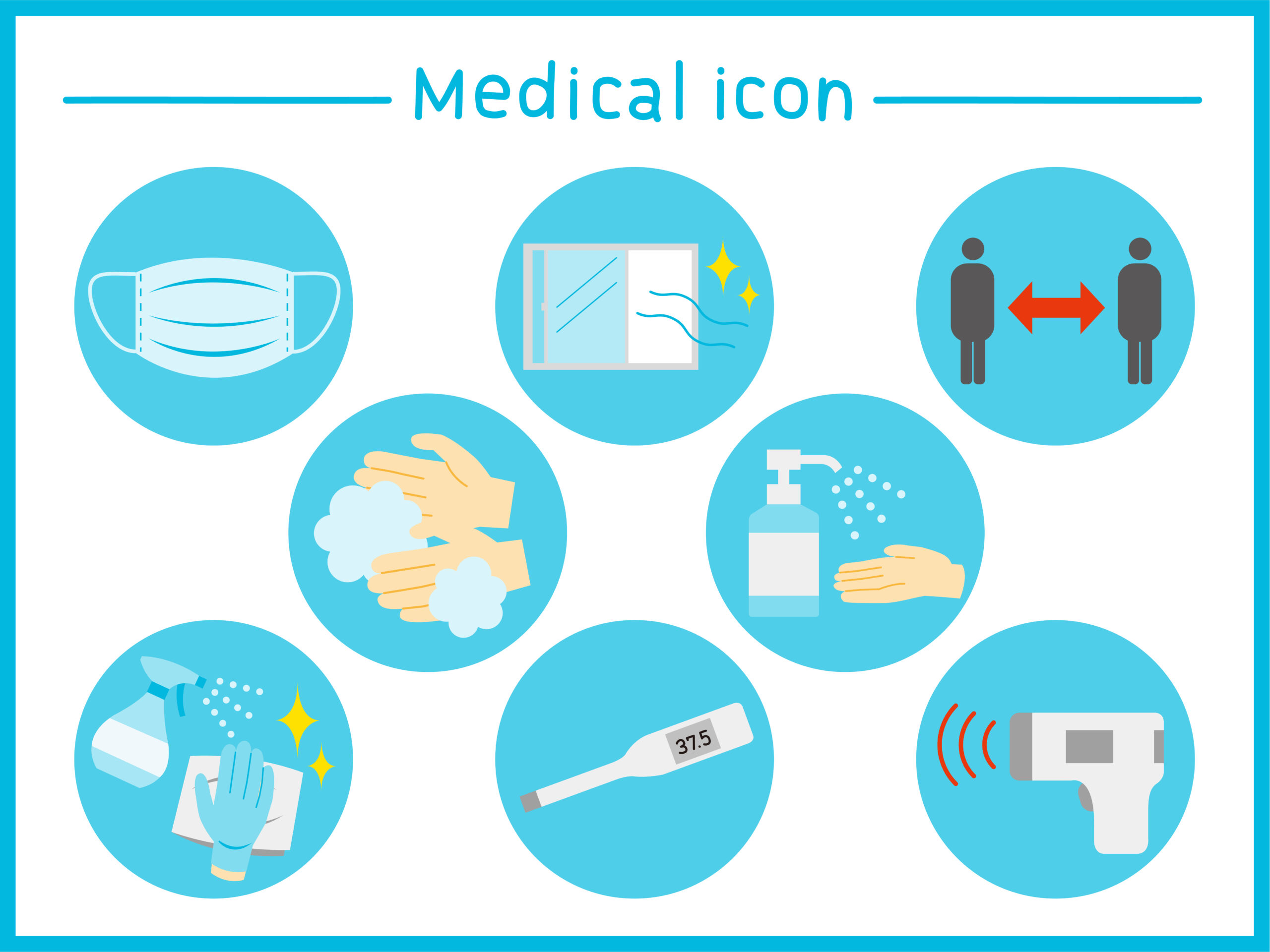
コメント