感染症診療において耐性菌への対応は、臨床現場で最も高度な判断が求められる領域のひとつです。抗菌薬の不適切使用によって耐性菌は増加の一途をたどり、今や「ポスト抗菌薬時代(Post-antibiotic era)」への危機感すら現実のものとなりつつあります。

本稿では、耐性菌の基本的な定義から代表的な菌種の特徴、有効な抗菌薬の選択肢、MIC(最小発育阻止濃度)の活用法について、医療従事者向けに体系的に解説します。
1. 耐性菌とは?

耐性菌(Antimicrobial-Resistant Organisms)とは、従来有効とされていた抗菌薬に対して感受性を失った、または感受性が低下した細菌のことです。
耐性化の主な機序は以下の通りです:
- 薬剤分解酵素の産生(例:β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼ)
- 薬剤の標的変異(例:PBP変異、DNAジャイレース変異)
- 修飾酵素(例:アセチル化、アデニリル化、リン酸化)
- 細胞膜透過性の低下(例:ポーリンの欠損)
- 排出ポンプ(efflux pump)の活性化

抗菌薬が効くっていうことは、①抗菌薬が病原体に取り込まれる、細胞表面の受容体に接着する②細胞分裂や細胞壁の合成を障害する③機能障害がおき病源体を破壊する。という流れになっており、それに対して抵抗性を見せるのが「耐性」なんだ。
2. 代表的な耐性菌とその特徴
✅ MRSA(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌と呼ばれペニシリン系、セフェム系などほとんど薬剤が無効だよ。
- 主な感染部位:皮膚・軟部組織感染症、肺炎、菌血症、人工物感染など
- 耐性機序:PBP2aの獲得によるペニシリン系・セフェム系への耐性
- 有効薬:
- バンコマイシン(注射薬)
- リネゾリド(経口薬、注射薬)
- テイコプラニン(注射薬)
- ダプトマイシン(注射薬)
- アルベカシン(注射薬)
- テジゾリド(経口薬、注射薬)
- 判定基準 :セフォキシチン ディスク拡散法 阻止円直径 ≦ 21mm セフォキシチン 微量液体希釈法 MIC ≧ 8μg/mL オキサシリン 微量液体希釈法 MIC ≧ 4μg/mL

保険適応ではないが、臨床的にはスルファメトキサゾール・トリメトプリムやミノサイクリン※が使用されるケースもある。
※適応外使用を推奨するものではありません。
✅ VRE(Vancomycin-Resistant Enterococcus)

バンコマイシン耐性腸球菌といってバンコマイシンに耐性化しているが、ペニシリン系が効くことがあり感受性を確認しよう!
- 主な感染部位:尿路感染、腹膜炎、菌血症など
- 耐性機序:VanA/VanB遺伝子によるD-Ala-D-Lacへの置換
- 有効薬:
- リネゾリド(経口薬、注射薬)
- アンピシリン(注射薬)
- ダプトマイシン(注射薬 高用量が推奨:適応外量)
- テジゾリド(経口薬、注射薬 適応なし)
- MIC参考値:
- バンコマイシン MIC ≧ 16 µg/mL(耐性)
✅ ESBL産生菌(E. coli, Klebsiella spp.)

この患者さんから「ESBL菌」検出されています。耐性菌ですよね!?
ここをタップ!

ESBLsは菌の名前ではなくて、広域に阻害できるβラクタマーゼを持っているということだよ!
- 主な感染部位:尿路感染、腹腔内感染、敗血症など
- 耐性機序:ESBL(Extended-Spectrum β-Lactamase)によるペニシリン系・セファロスポリン系の加水分解
- 有効薬:
- カルバペネム系(メロペネム、イミペネム)
- セフメタゾール(軽症例・尿路など一部では有効)
- セフタジジム/アビバクタム(新規βラクタマーゼ阻害剤配合)
- タゾバクタム/セフトロザン
- MIC参考値:
- ちょっと細かいので割愛します。
✅ CRE(Carbapenem-Resistant Enterobacterales)

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌のことで文字通り「カルバペネム耐性」の恐ろしい耐性菌です。
- 主な感染部位:尿路、肺、血流、創傷感染など
- 耐性機序:①カルバペネム分解酵素であるカルバペネマーゼ産生②ESBLやAmpCなどの広域β-ラクタマーゼ産生に加えて外膜蛋白の透過性が低下することでカルバペネムに耐性化する
- 有効薬:
- セフタジジム・アビバクタム(注射薬)(①の場合はアズトレオナムと併用)
- イミペネム・レレバクタム(注射薬)
- セフィデロコル(注射薬)
- コリスチン(注射薬 耐性菌最終選択肢)
- MIC参考値:(2025年4月改訂)
- メロペネム MIC ≧ 2 µg/mL
- カルバペネマーゼ産生を遺伝子検査等で確認
✅ MDRP(多剤耐性 Pseudomonas aeruginosa)

あらゆる薬剤に対して耐性を獲得した緑膿菌です。
- 主な感染部位:肺炎(特にVAP)、尿路感染、熱傷創など
- 耐性機序:
- AmpC β-ラクタマーゼ産生、ポーリン変異、efflux pump増強
- 有効薬:
- セフトロザン・タゾバクタム(注射薬)
- セフタジジム・アビバクタム(注射薬)
- イミペネム・シラスタチン+レレバクタム(注射薬)
- コリスチン(注射薬)
- MIC参考値:
- アミカシン:MIC ≧ 32 µg/mL
- イミペネム:MIC ≧ 16 µg/mL
- シプロフロキサシン:MIC ≧ 4 µg/mL
3. MIC(最小発育阻止濃度)の活用法

MIC(Minimum Inhibitory Concentration)は、菌の増殖を阻止できる最小の抗菌薬濃度を示します。これは治療薬選定の重要な指標であり、臨床分離株の感受性を評価する上で不可欠です。
✅ MICと臨床判断の関係
- 「感受性」でもMICが高めであれば薬効が不十分なケースも
- 血中濃度とPK/PDパラメータ(T>MIC、AUC/MICなど)とのバランスが重要
- 感染巣(肺、血液、中枢など)での薬剤移行性もあわせて評価

数字だけで見ないことが大事です。肺炎の喀痰培養を行い下記のような結果が出ました。
- シプロフロキサシン:MIC ≧ 4 µg/mL
- イミペネム:MIC ≧ 16 µg/mL

シプロフロキサシンの方が数字が小さいので効きますね!

喀痰培養を含む各種検査はin vitroといって試験管内のデータであって、「臓器移行性」を考慮していないため数字が小さいから効くってわけではないんだよ!
✅ PK(Pharmacokinetics:薬物動態)
薬物が体内に投与された後、どのように吸収・分布・代謝・排泄されるかを示します。
主なパラメータ:
- Cmax(最高血中濃度)
- Tmax(最高濃度到達時間)
- AUC(血中濃度-時間曲線下面積)
- t½(半減期) など
✅ PD(Pharmacodynamics:薬力学)
薬物が体内でどのように作用し、どの程度の効果を発揮するかを示します。
抗菌薬では、病原菌に対する作用の強さと時間的経過を扱います。
| 薬剤群 | 有効性の指標 |
|---|---|
| ペニシリン、セフェム、カルバペネム系 | T>MIC MICを超える時間の割合 |
| アミノグリコシド系 | Cmax/MIC 最高血中濃度とMICの比 |
| グリコペプチド、テトラサイクリン、フルオロキノロン、アジスロマイシン系 | AUC/MIC 濃度×時間の総量とMICの比 |
4. まとめと臨床への示唆
耐性菌感染症の診療では、単に「感受性があるかないか」ではなく、菌種・耐性機構・有効薬・PK/PD・MICといった多角的視点からの治療設計が求められます。
特にMICの解釈は、抗菌薬の投与設計(量・間隔)を考える上で極めて重要であり、薬剤師や感染制御チームとの連携の中核となります。
耐性菌対策は、「治療」だけでなく「予防(感染対策)」「制御(抗菌薬適正使用)」の視点からも重要です。今後もASTやICTを通じて、施設全体での耐性菌マネジメントが求められます。

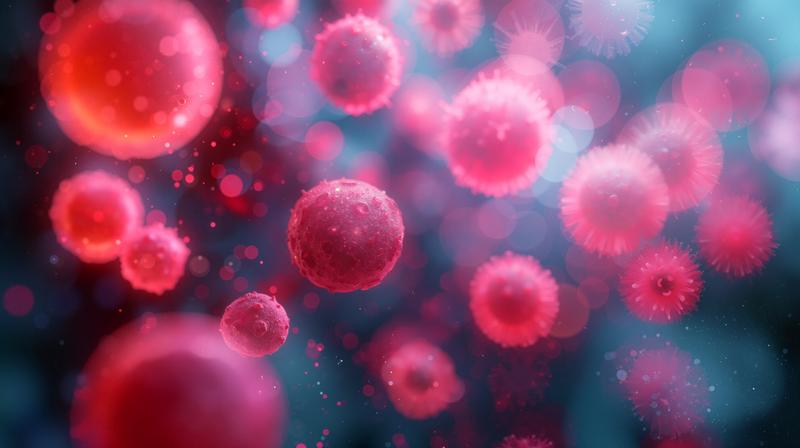

コメント