感染症と聞くと、
新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルスなど、さまざまな病気が思い浮かびます。医療従事者として感染症に正しく対応するには、「感染症とは何か?」という基本的な理解が不可欠です。
今回は、**感染様式(どのように感染が広がるのか)**と、感染症の原因となる微生物の大きさという、基礎中の基礎を整理してご紹介します。
※ウイルスや細菌のあとに(〇類)としたのは感染症法上の分類です。
感染様式とは?
感染様式とは、

「病原体がどのようにして人から人へ、あるいは環境から人へと広がるか」を示したものです。
感染経路とも呼ばれ、感染症対策を考えるうえで非常に重要な視点になります。
感染様式は主に以下のように分類されます:
① 接触感染(直接・間接)

もっとも基本的な感染経路です。
- 直接接触感染:感染者の皮膚や体液と直接触れることで感染する(例:ヘルペス、疥癬)。
- 間接接触感染:感染者が触れた物品(ドアノブ、ベッド柵など)を他者が触れることで感染する(例:ノロ(5類)ウイルス、MRSA(5類))。

手指衛生がもっとも重要な感染対策です。
② 飛沫感染

感染者の咳やくしゃみなどで放出された**大きな飛沫(約5μm以上、落下速度30~80cm/sec)**が、他者の粘膜に付着することで感染します。
- 飛沫は1~2m以内に落下するため、近距離での接触が問題になります。
- インフルエンザ(5類)ウイルス、レジオネラ(4類)、肺炎球菌(5類)、流行性耳下腺炎(5類)ウイルス、風疹(5類)ウイルス、COVID-19(一部)などが該当。

対策としてはマスクの着用、距離の確保、咳エチケットが有効です。
③ 空気感染(飛沫核感染)

飛沫が蒸発してできる**微細な粒子(飛沫核、5μm未満 落下速度0.06~1.5cm/sec)**が空気中に長時間浮遊し、それを吸い込むことで感染します。
- 空気感染を起こす代表的な病原体は限られており、結核菌(2類)、水痘(5類)ウイルス、麻疹(5類)ウイルスなどがあります。
- 一般的なマスクでは防げないため、N95マスクや陰圧室が必要となるケースもあります。

N95マスクとは「95」は0.3μmの粒子を95%以上除去できる高性能マスクのことです。
④ 経口感染(糞口感染)

※お寿司屋さんはしっかり消毒を行っております

病原体が食べ物や水、または口に入ることで体内に取り込まれ感染します。
- 代表例:ノロ(5類)ウイルス、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O157(3類)。
- 対策としては調理衛生、食材の加熱、手洗いの徹底が重要です。
⑤ 血液・体液媒介感染(血中感染)


血液、体液、注射針などを介して病原体が体内に侵入します。
- 代表例:B型(5類)・C型(5類)肝炎ウイルス、HIV(5類)。
- 医療現場では、**針刺し事故や体液曝露の対策(PPEの着用など)**が欠かせません。
- 以前は輸血や注射針の使いまわしが問題になりました。
⑥ 媒介物感染(ベクター感染)
蚊やダニなどの「媒介動物(ベクター)」が病原体を運び感染します。
- 例:マラリア(4類)(蚊)、ツツガムシ病(4類)(ダニ)、デング熱(4類)、ジカ熱(4類)。
- 日本でも近年、温暖化などにより媒介動物の分布が変わってきており、注目される感染様式です。
- 海外からの貨物に混入し、日本でも流行することがあります。
微生物の大きさ感覚をつかもう!
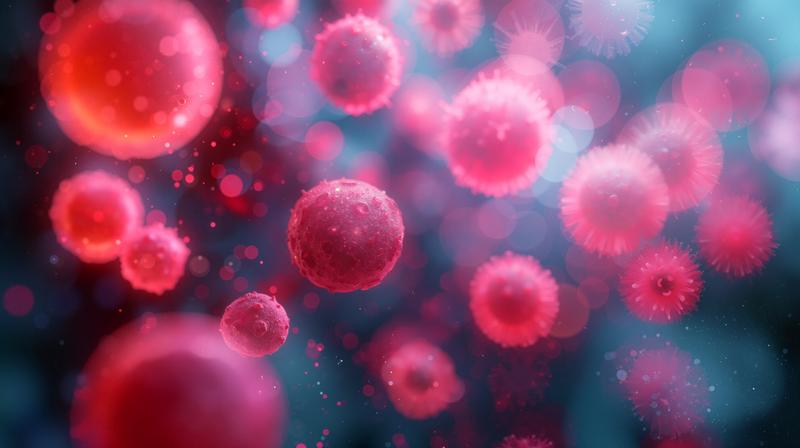
感染症の原因となる微生物は目に見えないほど小さい存在ですが、そのサイズには幅があります。下記は、代表的な微生物のサイズを示したものです。
| 微生物種別 | サイズ(おおよそ) | 例 |
|---|---|---|
| ウイルス | 20〜300nm | ノロウイルス(30nm)、インフルエンザ(100nm) |
| クラミジア | 200~800nm | 感染型200~300nm 増殖型500~800nm |
| リケッチア | 幅0.3~0.5μm長さ0.8~2.0μm | |
| 細菌 | 0.5〜5μm | 大腸菌(約2μm)、肺炎球菌(1μm) |
| 真菌 | 数μm〜数十μm | カンジダ(約4〜6μm)、アスペルギルス |
| 原虫 | 数μm〜100μm | マラリア原虫(約10μm) |
| 寄生虫 | 1mm以上(肉眼で見えることも) | 回虫、蟯虫 |
※1μm=1,000nmです
このサイズ感をイメージすることで、なぜウイルスにはサージカルマスクでは限界があるのか、細菌はなぜ抗生物質で治療可能なのか、などが理解しやすくなります。
感染対策は「病原体」と「感染様式」に合わせて
感染症対策は、「すべてに同じ対応をする」わけではありません。
病原体の種類やサイズ、感染様式に応じて、以下のように対策を切り分ける必要があります。
- 接触感染 → 手指衛生、環境清拭
- 飛沫感染 → マスク、距離の確保
- 空気感染 → N95マスク、陰圧室
- 経口感染 → 食品衛生、手洗い
- 血液媒介感染 → 手袋、ガウン、シャープスボックス

また、**微生物のサイズに応じた物理的対策(マスク、フィルターなど)**も理解しておくと、院内感染対策の精度が上がります。
まとめ
感染症の基本である「感染様式」と「微生物の大きさ」をおさらいしました。
医療現場では、病原体が見えないからこそ、正しい知識と想像力が何よりの武器です。薬剤師としても、抗菌薬の選択や感染制御チームでの活動、患者さんや他職種への説明など、幅広い場面でこの基礎知識が生かされます。
これからも、現場に活きる感染対策の情報をわかりやすく発信していきます。
次回は「抗菌薬の使い分け」や「耐性菌の基礎知識」についても取り上げる予定です。ぜひご覧ください!


コメント