2025年は蚊に媒介されるチクングニア熱が世界的に流行しており、9月末までの全世界の患者数は26万人で、昨年に比べて大幅に増加しました。とくに米州ではブラジルを中心に22万人が発生しており、アジアでもインドやインドネシアで報告数が多くなっています。また、今年は温帯地域での流行も発生しており、中国の広東省では9月下旬までに16,000人、ヨーロッパでもフランスで700人、イタリアで300人の国内感染例が報告されました。
チクングニア熱とは?
チクングニア熱とはチクングニアウイルスによって引き起こされる四類感染症です。チクングニアウイルスはトガウイルス科アルファウイルス属に分類されるRNAウイルスで、ネッタイシマカやヒトスジシマカなどの「蚊」によって媒介されることが知られている。

媒介動物は身近にいる「蚊」です。
感染経路と潜伏期間
感染経路としては感染した人の血液を吸った蚊が、別の人にウイルスを運ぶことで感染が拡がります。
潜伏期間は2〜12日、平均で3〜7日程度とされ、症状は急激に出現します。人から人への直接感染は基本的にはありません。母子感染や輸血などによる理論的リスクは存在しますが、極めて稀です。

人から人にうつる感染症ではないんですね!
日本で拡がる可能性は?

日本国内にもヒトスジシマカが広く分布しており、温暖な気候と合わせて、理論上は感染が拡がる可能性があります。特に夏季の高温多湿な時期には蚊の活動も活発になるため注意が必要です。
ただし、現時点で日本国内においてチクングニア熱の市中感染(自家感染)は報告されておらず、過去の症例もほとんどが海外からの輸入例です。日本でも今年の輸入例は9月末までに19人で、昨年の年間輸入例(10人)をすでに超えています。感染が拡大するためには、ウイルスを保有した蚊が一定期間生存し、複数人に感染させる必要があります。
今後も温暖化や渡航者の増加などにより、局地的な感染リスクは高まる可能性があります。

海外からの貨物に媒介動物が載せられてきた。なんてこともありました。
症状の特徴

チクングニア熱は「急性の発熱」と「激しい関節痛」が特徴です。その他にも以下のような症状がみられます。
- 発熱(38~40℃程度)
- 関節痛・筋肉痛(手足、膝、腰など)
- 倦怠感・頭痛
- 発疹
- 吐き気・下痢
特に関節痛は激しく、「チクングニア」という名前も、現地の言語で「曲がった姿勢」を意味する言葉が由来です。多くの人は1週間程度で回復しますが、一部では関節痛や腱の炎症が数週間から数か月にわたって持続することもあります。
高齢者や基礎疾患のある人、小児では重症化することもあり、稀に脳炎や視覚障害などの合併症が報告されています。
媒介する蚊とその対策

チクングニア熱を媒介するのは主にネッタイシマカとヒトスジシマカです。これらの蚊は日中に活動し、都市部でも繁殖しやすいという特徴があります。特に水たまりや植木鉢の受け皿、古タイヤなどに卵を産むため、屋外の水の管理が重要です。
中国広東省では今回の流行を受けて、蚊の駆除に加え、蚊の幼虫を食べる「カニバリ蚊」や、罠、殺虫剤の使用など多角的な蚊対策が実施されています。

ご自宅のお庭でも「水たまり」なるようなところは「蚊」の格好の住まいになってしまいます。
治療法と予防手段

現在、チクングニア熱に対する特効薬や抗ウイルス薬は存在していません。治療は以下のような対症療法が中心です。
- 解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンなど)
- 水分補給と安静
- 必要に応じて入院管理(重症例)
また、ワクチンも一般には流通していません。一部の国では承認済みのワクチンが存在しますが、広く普及するには至っていません。
予防の基本は「蚊に刺されないこと」です。以下のような対策が有効です。
- 肌の露出を避ける服装
- 虫よけスプレーの使用
- 室内の蚊取り装置や網戸の活用
- 不要な水たまりの除去
今後の注意点とまとめ
現在、中国でのチクングニア熱流行は抑え込みが進められていますが、都市部の高密度な人口、気候条件、蚊の繁殖状況などから今後の感染動向に引き続き注意が必要です。
日本国内ではまだ感染の広がりは見られませんが、温暖化やグローバルな人の移動により、今後のリスクはゼロではありません。医療機関・自治体ともに、感染症サーベイランスや蚊媒介感染症に対する備えが求められます。
出典:厚生労働省 検疫所 FORTH
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
東京医科大学病院 渡航者医療センター
2025.10.30 一部改変


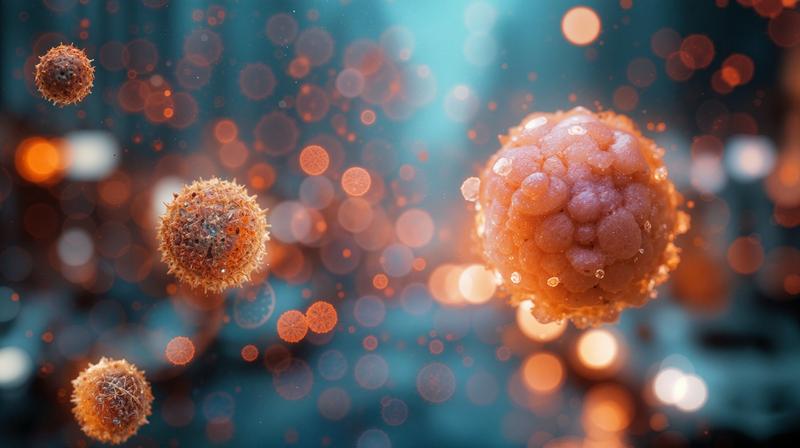
コメント