こんにちは、薬剤師ブロガーのIWAKIです。
今回は、認定資格取得の際に誰もがつまずく「症例報告」の書き方について、感染制御認定薬剤師(PIC)と抗菌化学療法認定薬剤師(化療認定)の違いを中心に解説していきます。
どちらも抗菌薬適正使用に関連する専門資格ですが、症例報告に求められる視点やスタイルには微妙な違いがあります。これから申請を目指す方、症例の書き方に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
 | 薬剤師のための感染制御マニュアル 第5版 [ 一般社団法人 日本病院薬剤師会 ] 価格:7370円 |
感染制御認定薬剤師の症例報告:チーム医療における「介入」を強調
✅ 書き方のポイント
- 患者背景(原疾患、感染症の種類、既往歴など)を明確にする
- 抗菌薬選択やTDMへの関与、医師への提案の内容
- 提案が受容されたか、アウトカムはどうだったか
👑必要な項目
- 抗菌薬適正使用支援)プログラムに該当する活動により、薬剤師として貢献した事例。
- 環境ラウンドへの同行などにおいて、薬剤師として薬学的知識、技術などを活用して感染予防・感染対策に貢献した事例。
- TDM を実施した症例。
- 感染制御や抗微生物薬適正使用に関する、組織内マニュアル・手引き等の作成・改訂や、それらの普及啓発に資する組織内での 取り組み事例。
- 上記の①から④に該当しないこと。
✍ フォーマット例(400字程度)
当院ではこれまで、速乾性アルコール手指消毒剤(以下、消毒剤)を各病室前、○○などに配置し手指衛生の徹底を図ってきた。しかし、近年は消毒剤の使用量の減少が課題となっていた。この状況を受けて、ICTにて協議を行い、患者との接触機会が多い看護師及びリハビリテーションスタッフを対象に、消毒剤の個人携帯を導入することが決定された。申請者は、この取り組みにおいて消毒剤および携帯用ポシェットの発注と払い出しを担当した。個人携帯による運用は翌月より開始され、各病棟のリンクナースおよびリハビリテーションスタッフの主任が携帯の実施状況や使用状況を集計し、ICTに報告する体制が構築された。申請者はこの集計結果をJ-SIPHEに入力し、ICTでの共有を行っている。取り組み開始後は、職員の手指衛生に対する意識向上が見られたこともあり、消毒剤の使用回数は平均〇回から○○回と増加した。こうした成果は、年2回開催される院内感染対策研修会において報告され、さらなる意識向上と手指衛生の徹底に活用されている。
💡 コツ
- 「自分がどう動いたか」を明確に記述すること(自分が介入したところにアンダーライン)
- ただの記録にならないよう、薬剤師の役割と判断力を見せる
- 検査値には単位を必ずいれる
- 指定された症例数守って記載する
抗菌化学療法認定薬剤師の症例報告:処方設計と考察がキモ
✅ 書き方のポイント
- 抗菌薬の選択理由とその根拠(文献やガイドライン)
- PK/PDやTDMを活用した処方設計
- 治療結果の考察と今後への示唆
- 菌名は学名で記載。
- 感染症治療薬の名称は日本化学療法学会の指定する略号を使用。
✍ フォーマット例(400字+考察)
直腸がん術後 〇 か月が経過した患者。手術部位を原因とする感染性腹膜炎の診断で入院。抗菌薬治療として、入院時より SBT/ABPC3 g × 2 回/day で加療開始、継続されていた。入院 〇日目、薬剤管理指導実施時に本患者のクレアチニンクリアランス(Ccr)値がCockcroft-Gault 式より 90.5 mL/min(体重 67 kg、血清クレアチニン値 0.74 mg/dL)と計算されることを確認。このときの CRP 値は25 mg/dL と、入院時(16 mg/dL)より上昇していた。しかし、血
圧を含めバイタルサインに異常は認めず、入院時の腹水培養から検出されたのは Enterococcus faecalis のみであった。主治医はより広域なスペクトルを有する抗菌薬への変更を予定して〇〇たが、上記腎機能を考慮して SBT/ABPC の 3 g×4 回/day への増量を提案した。 提案は速やかに実施され、その 2 日後(入院 〇 日後)には臨床的に改善と判断され、入院 1日目に CRP 値は 0.9 mg/dLまで低下し、治療は完了となった。抗菌薬終了以降も腹膜炎の再発は認めていない。考察
入院当初、SBT/ABPC の添付文書記載の用法用量である 3 g×2 回/day に設定されていたが、
SBT/ABPC の pharmacokinetics/pharmacodynamics (PK/PD)パラメータは time above MIC であり、頻回投与が必要となること、さらには SBT/ABPC の体内動態特性、すなわち腎排泄型薬剤としての特性を考慮して患者腎機能に応じた投与間隔の設定が必要となること、これら 2 点を念頭に至適投与設計を探索した。当該患者の Ccr 値がきわめて良好であること、ならびにサンフォード感染症治療ガイドの記載内容に基づき、3 g×4 回/day を推奨した。結果として、この処方への変更後すみやかに容体の改善が認められたことから、PK/PD パラメータおよび腎機能に応じた用法用量設定の受容性を再認識できた。また、抗菌薬の効果が乏しい場合、ともすれば広域スペクトルの薬剤に変更しようとする雰囲気が現場にはあるが、効果不良の原因を洞察し、緊急性や同定された菌種を鑑みた上で抗菌薬を選択し、さらには至適用法用量に設定することの重要性を学ぶことができた。
 |
価格:3960円 |
![]()
💡 コツ
- 「なぜその薬剤を使ったのか?」を論理的に説明
- 単なる報告で終わらせず、専門家としての視点で考察を加える
- 参考にした文献やガイドラインを記載する
症例報告の違いを比較してみた
| 項目 | 感染制御認定薬剤師(PIC) | 抗菌化学療法認定薬剤師(化療認定) |
|---|---|---|
| 強調点 | 介入行動・TDM・提案力 | 処方設計・理論的根拠・考察 |
| スタイル | 簡潔な事例(20例) | 詳細かつ考察付き(15例) |
| 審査視点 | チーム医療への貢献 | 臨床的判断と薬物治療設計力 |
まとめ:症例は“あなたの実力の証明書”
どちらの症例報告も、単なる業務の記録ではありません。「薬剤師としての判断・行動・成果」を的確に伝えることが合格への近道です。
臨床経験が浅くても、「なぜそうしたのか」を明確に言語化することで、審査側に実力をアピールできます。採点者は申請者が”何を” ”どう” ”考えたか” を求めています。誤字脱字をしない、単位を間違えない、背景をしっかり記入することが大事です。
IWAKI的には化学療法認定薬剤師のほうが、内容がコアであり考察もあるので症例集めが大変だったと記憶しています。下もチェックしてみてください★
【比較解説】感染制御認定薬剤師と抗菌化学療法認定薬剤師、どっちを目指す?違いと選び方
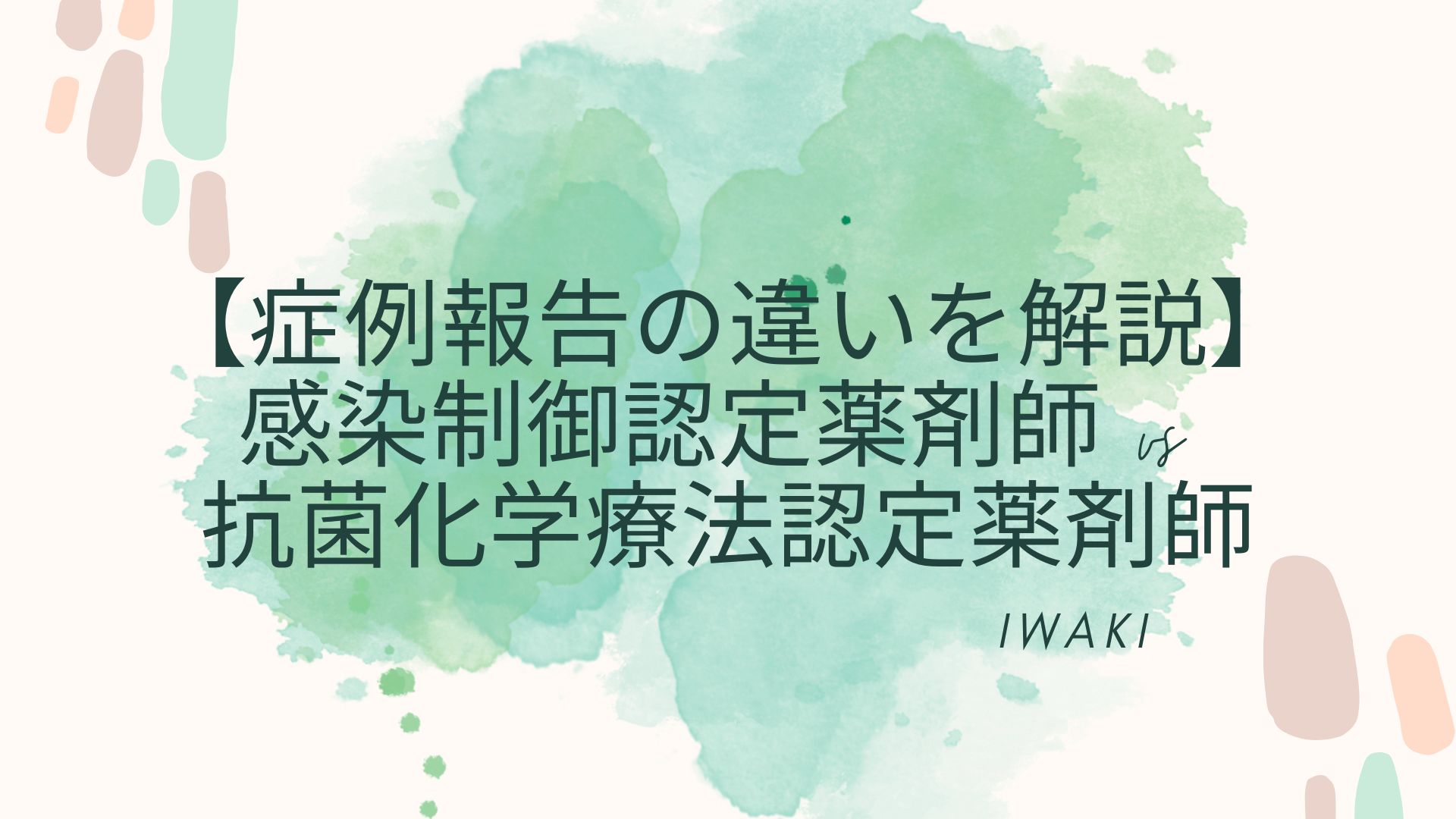
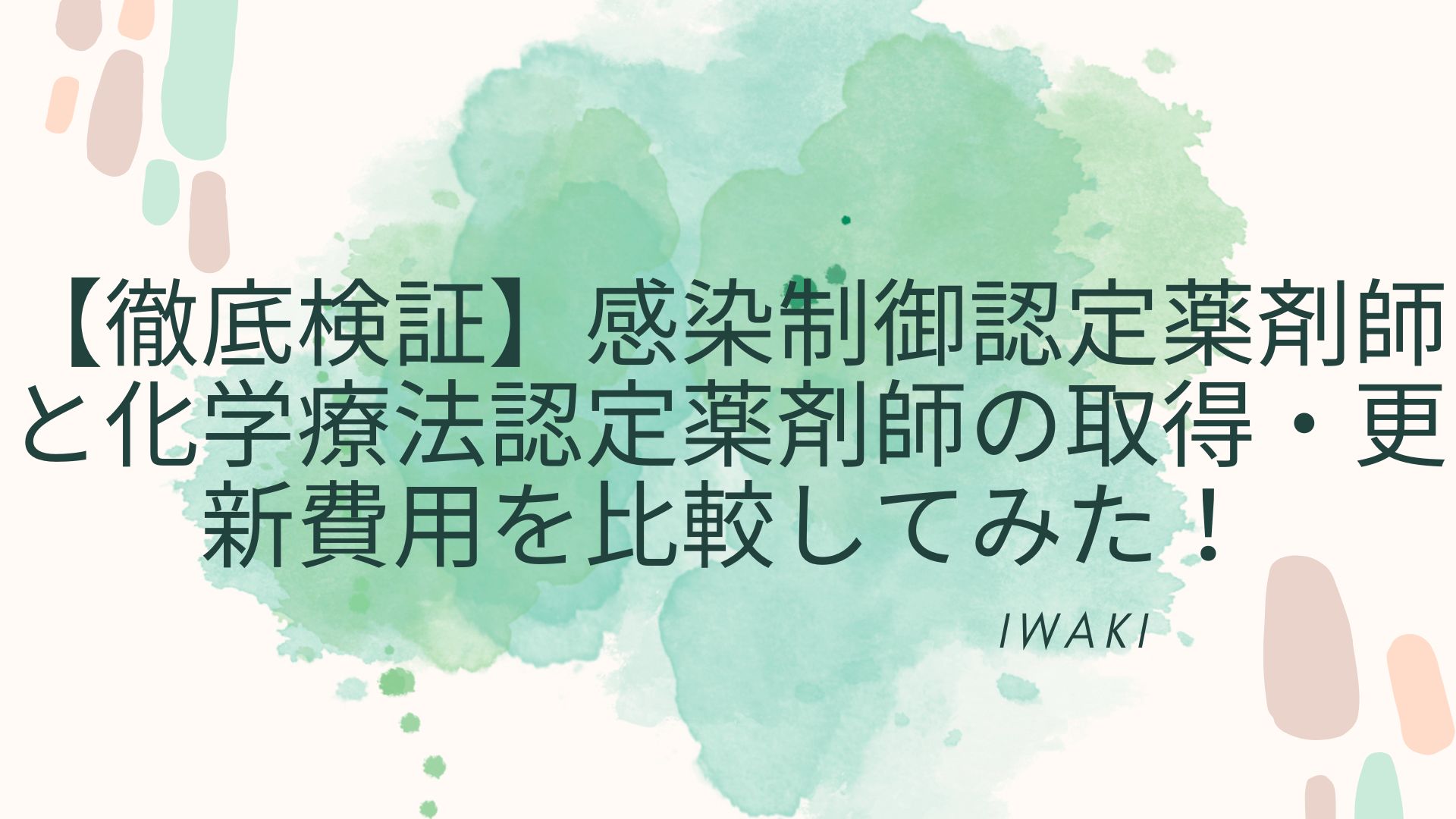
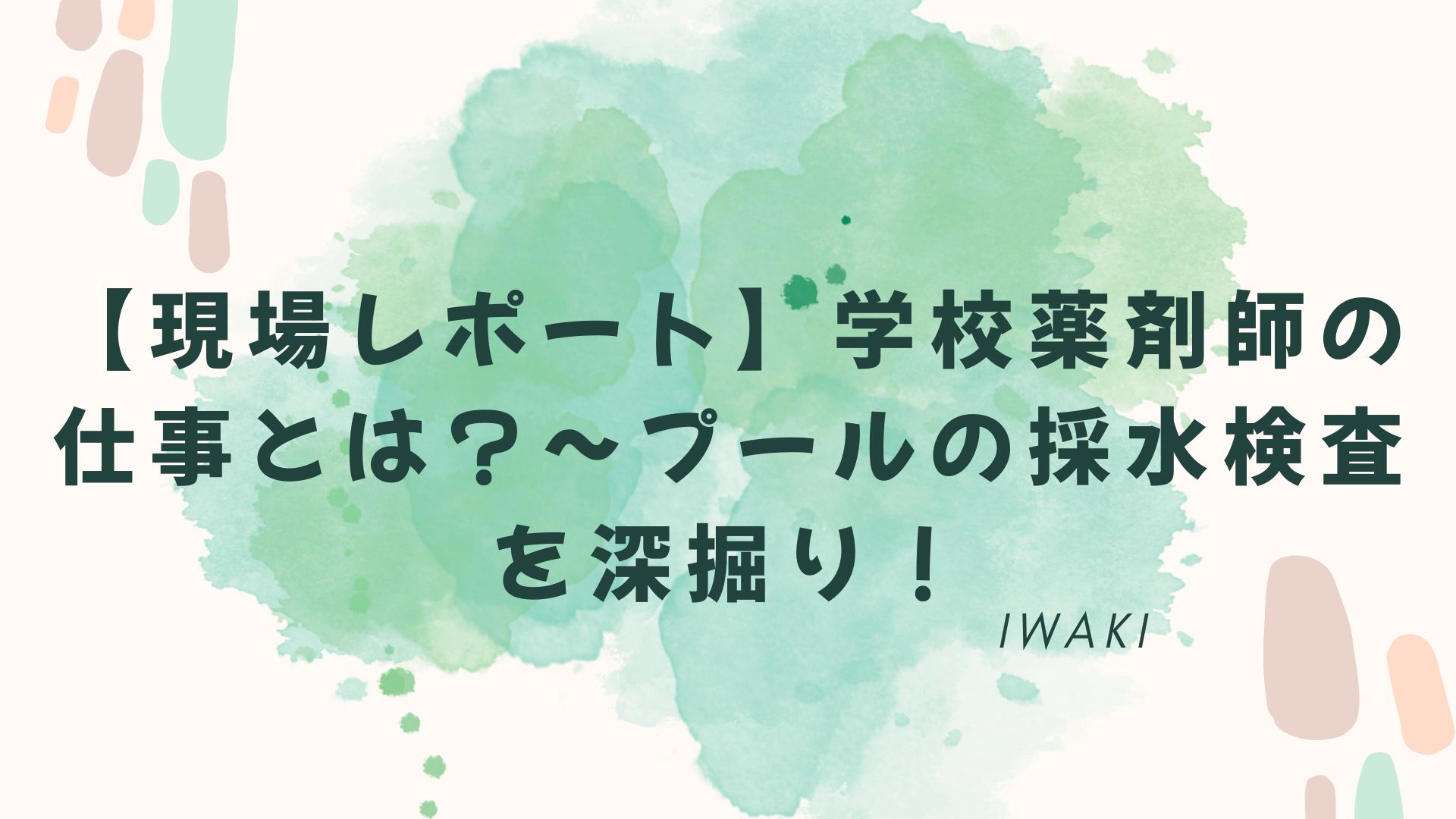
コメント