感染対策に特化した薬剤師資格「感染制御認定薬剤師(PIC)」。
この記事では、取得に必要な条件・費用・更新時の注意点を、現役薬剤師の視点からわかりやすく解説します。薬剤師になった!それがゴールではありません。薬剤師はジェネラリストでありながら、スペシャリストを目指して研鑽をつんでいきましょう。
🎓 新規取得に必要な9つの条件
- 薬剤師免許の保有
- 実務経験3年以上+薬剤師会会員
(日本病院薬剤師会、日本薬剤師会、日本女性薬剤師会など) - 感染系学会の会員であること
(日本薬学会、日本医療薬学会、日本TDM学会、私は日本化学療法学会に加入しています) - 病院薬学認定薬剤師の資格保有(または日本医療薬学会の専門薬剤師)
- 病院・診療所で感染制御業務を3年以上実施(直近1年以上継続)
- 20件以上の感染制御介入症例を報告可能
- 講習受講(20時間=10単位以上) ※日病薬主催のものを1回以上含む
- 施設長・病院長の推薦
- 筆記試験合格(合格率70〜80%)

IWAKI
症例はしっかり書けるように準備しておきましょう。試験は指定されたテキストをしっかり読み込めば大丈夫!
💡 症例報告のコツ
- TDM(薬物濃度モニタリング)を行ない、適切な管理をしている→ただの血中濃度測定ではなく、測定結果に対してどうコミットしたかを明確に記載できる。
- 医師に対し、抗菌薬使用について適切な提案・助言をしていること
→「医師の判断にどう影響したか?」を具体的に記載すると評価されやすいです。 - 院内研修会を主催、薬剤部内に感染制御に関する指導を行っていると事例が書きやすい
- サーベイランスに参加し、その内容を院内で共有している。さらに、サーベイランスによって院内が「どう」変わったか記載できる。
- 薬物間相互作用(カルバペネムとバルプロ酸など)の症例はただの疑義照会にならないように注意する。

IWAKI
院内の感染制御に関わる業務(研修会の開催)に関してはいつ頃、どのような規模で、何人集まったとか正確な情報を残しておこう。
🔁 更新要件(5年ごと)
- 会員資格の継続
- 病院薬学認定薬剤師などの資格を維持
- 更新申請時において、日本薬学会、日本医療薬学会、日本臨床薬理学会のいずれかの会員であり、かつ、日本TDM学会、ICD制度協議会に加盟している学会・研究会のいずれかの会員であること。
- 感染制御業務を続けている
- 講習会で30単位以上(12単位は日病薬主催)取得
- 感染制御事例10例以上報告
- 全国学会や病院ブロック大会での発表または論文発表(共同発表でも可)

IWAKI
日病薬主催の感染制御専門薬剤師講習会に数回出て単位を貯めるのがコツです。学会に参加するだけで単位がたまらなくなりました。(R6年6月~)
💸 費用の目安
| 費用項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 認定審査料 | 約10,000〜15,000円 |
| 認定料 | 約20,000円 |
| 講習受講料 | 講習内容による |
| 5年間の総額(日病薬+関連学会の年会費含む) | 約100,000〜200,000円 |

IWAKI
日本病院薬剤師会+感染系学会+薬学系学会の学会年会費が重くのしかかります。経費なども鑑みて新規申請・更新申請をしましょう。
✅ まとめ
- 感染制御認定薬剤師は、症例報告とチーム活動が鍵。
- 講習単位と発表実績の管理が更新では特に重要。
- 費用や単位取得に関して更新まで視野に入れて計画的に取得することが大事。
- 単位収集は余裕を持って!学会参加だけでは取得できない時代になっています。
- 新規申請時には所属学会は日本病院薬剤師会+1個でよかったが、更新時には+2個にしなければならない。
🎤 経験者の声(一例)
IWAKIは、新規取得時に近隣の感染制御専門薬剤師に症例を確認してもらいました。
業務の中で記録をコツコツ取っておくことが、申請の成功につながります。地味にお金がかかるなって感じです。研修単位に取得はWEB参加もできていい時代にはなっていると思います。
なかなか申請に係る費用や研修会費などを職場が負担してくれるところは少ないでしょう。現状、「この資格」がないと算定できないという「資格」まで至っていません。私も病院に交交渉をした結果、認定試験受験時の交通費と受験費用を工面してもらえました。若い人に進めるにあたって費用の壁は大きいと思います。
2025年8月14日 一部追記
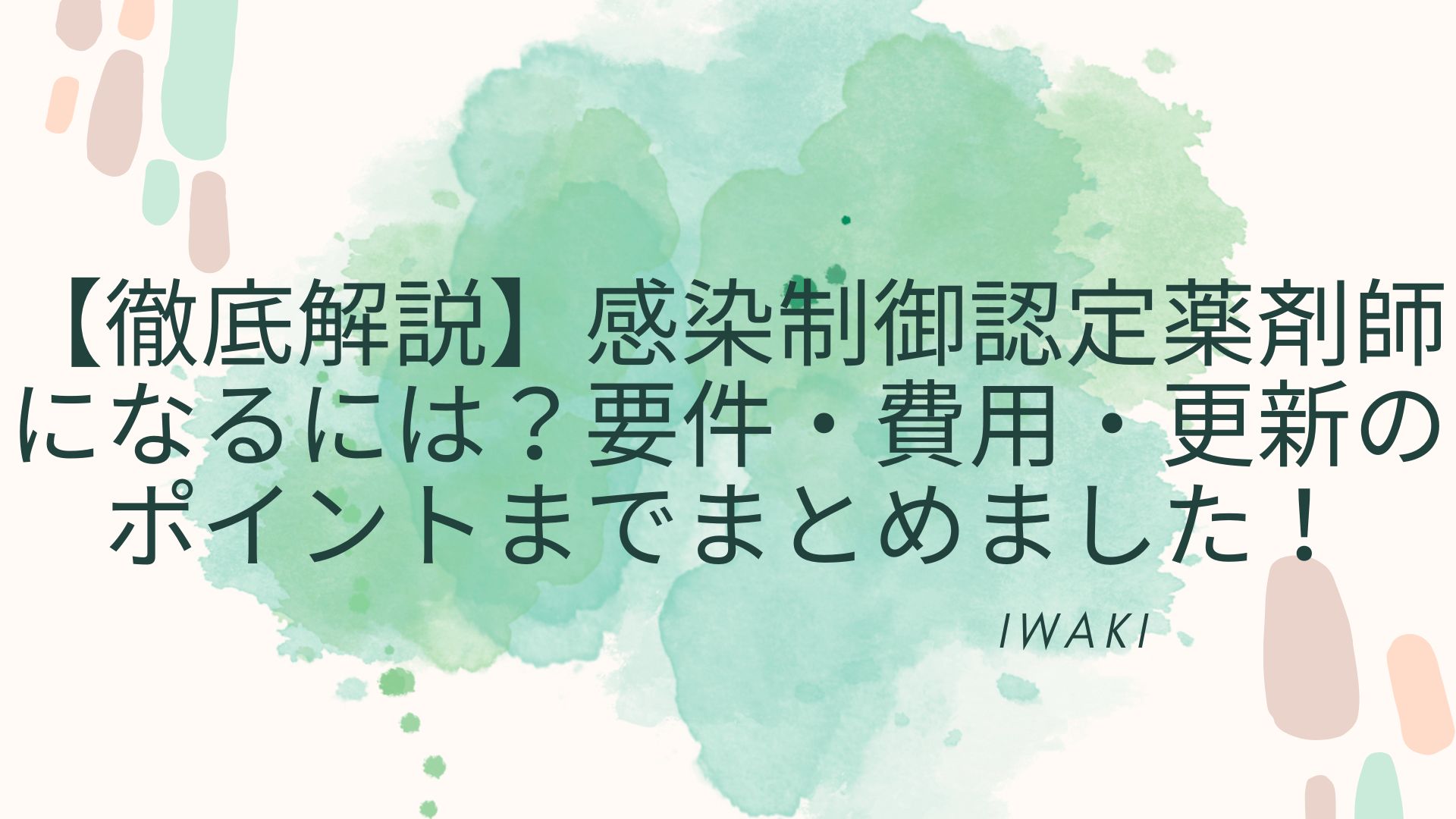
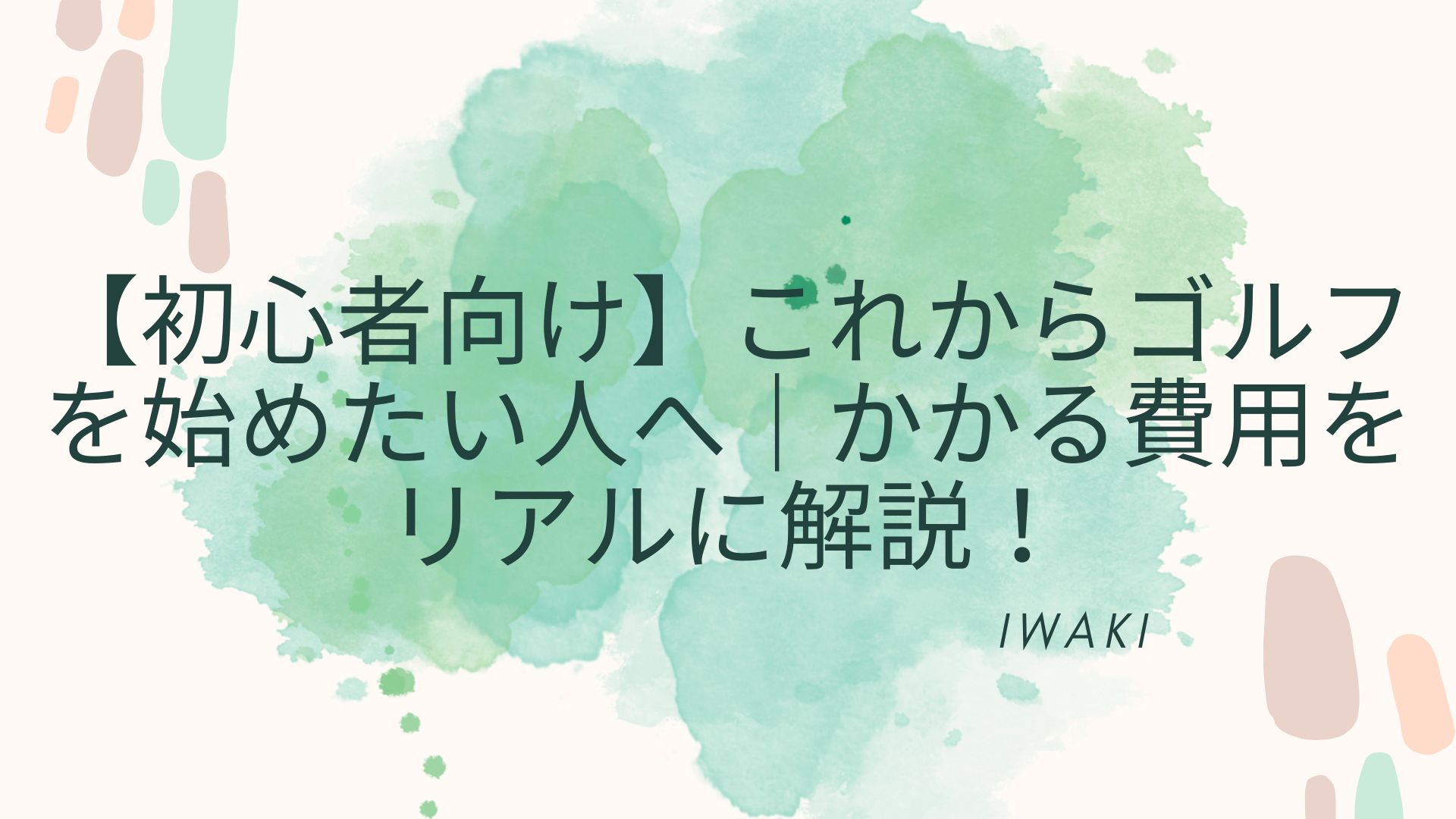
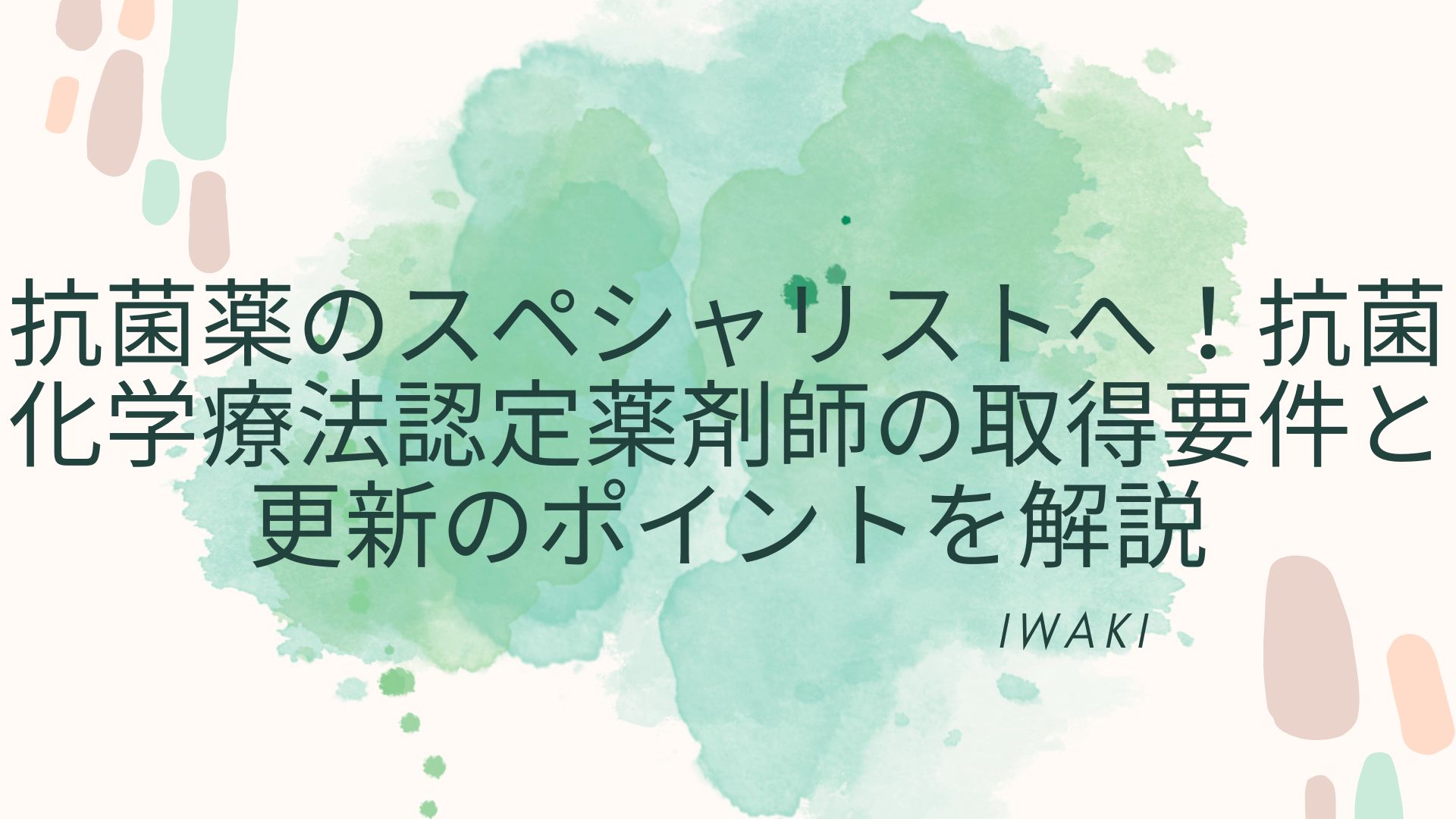
コメント